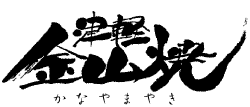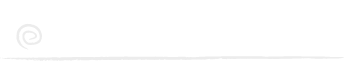窯焚き中
こんばんはちゅうばちです。
窯焚き二日目。今日の準夜の窯焚き当番です。
薪窯の窯焚きは当然ながら薪で温度を上げて行きますが、薪は人の手でくべなければなりませんから交代で窯焚きに当たります。
今回は5連窯で7日間の窯焚きですから、延べ17人で窯を焚きます。

急激な温度上昇は避けなければならない。特に窯に湿気があるうちはゆっくりと。なぜなら水が水蒸気になるときの体積の膨張エネルギーはとても強力だから。極短時間に起こる体積の膨張は爆発的で、作品や窯を破壊しかねない。
金山焼のやきものは食器が主力商品です。灰被りなどのダイナミックな表現は商品が限定されてしまいますから、桟切りが向いています。
この桟切りを出すために各部屋の焚き終わりのタイミングで、窯の温度がまだ高いうちに炭入れのをします。

窯の構造が良ければ、薪はどんな形をしていても関係がない。薪の種類と形を選ぶとすれば、1100℃を越えて最後の攻めの辺りだろう。まあそれも窯焚きのテクニックがあれば関係ないんだけど。大事なのは薪が乾いているってこと。
この作業にも人手が必要で、一度に4人から6人程が作業に携わります。5連窯の場合は5部屋あるので部屋ごとに炭入れの作業をしに人が集まってきます。
要するに薪窯は人が沢山いないと、簡単には焚けないということで、みんなで協力して金山焼を作っています。